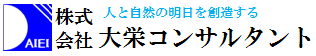Message
メッセージ
大栄コンサルタントの宝は、
みなさんです 。
社会から日々求められるご要望に応えるために、新たな知識や技術、考え方のアップデートが常に必要です。その実現に向けて、考え方や理念に共感していただける新たな仲間との出会いを求めています。一人ひとりの可能性を探り、圧倒的なスピード感で超成長させ、輝かすために全力を尽くす所存です。みんなそれぞれ違っていい。人生の主役となって、輝かしい経験と仕事を手に入れてください。
代表取締役 川満秀樹


会社概要
| 会社名 | 株式会社 大栄コンサルタント |
| 代表者 | 川満秀樹 |
| 電話番号 | 098-876-3373 |
| FAX | 098-875-2072 |
| 所在地 | 〒901-2134 沖縄県浦添市字港川412番地の4 ▶Googlemap |
| 設立 | 1992年12月 |
| 資本金 | 1,200万円 |
| 決算期 | 毎年9月末日 |
| 従業員 | 15名(令和7年3月現在) |
| 資格 | 技術士4名、RCCM7名、その他 ※延べ人数 |
| 登録 | 建設コンサルタント業者登録許可(建30第6221号)、測量業者登録認可(第(6)21589号) |
| 内容 | 土木設計(一般、港湾、農林、水産)、陸上測量・海上測量、地質調査・磁気探査、発注者支援(現場技術、開発申請) |
| 取引先 | 沖縄県、沖縄県内市町村、沖縄総合事務局、その他民間事業者等 |
※当社は、役職員あわせて15名の小規模な組織です。総務部、設計部、企画部の3部と持続可能な沖縄の発展に関する事業を行う、サステナビリティ事業室があります。
→会社案内用パンフレットはこちらです。
→サステナビリティ事業室の紹介はこちらです。
Focus
こんな方に当社をお勧めします
下記の記事は、大手の建設コンサルタントから当社に転職した職員が、自身の経験や社内外のベテラン技術者との話に基づいて作文したものです。県外からのUIターンの方など、転職をお考えの方にお読み頂けると幸いです。
<多忙な建設コンサルタントからの転職を考えている方>
例えば、
・家庭との両立や年齢等の都合によって、働く時間を定時や数時間以内の残業に抑え、休みもしっかり取りたい。そのうえで、今まで培った経験もしっかり活かしたい。
・今の勤め先では、実質的に実務をしっかりこなしている。しかし、せっかくRCCMの資格を持っていても、組織体制の都合によって管理技術者となる機会になかなか恵まれない。
・以前は実務をバリバリこなしていたが、管理職になってからはすっかり実務が縁遠くなり、物足りなさや将来への不安を感じている。縁あって沖縄に戻る(来る)ことをきっかけに、実務者に返り咲いて手に職を取り戻したい。
・これまで分業制によって限られた分野の設計業務に携わってきたが、その他分野の設計業務をはじめ、色々な仕事の機会があるこじんまりした職場に魅力を感じる。
<異業種の建設会社等からの転職を考えている方>
例えば、
・これまで設計や施工管理の仕事をしてきたが、立場を変えて建設コンサルタントの仕事に取り組んでみたい。
・設計業務、施工管理業務、営業等の経験を積んできたが、好きな設計業務に特化して仕事をしていきたい。
・定年を迎えるまでに沖縄に戻り(来て)、体力的に有利な内業主体の建設コンサルタントの仕事に馴染んで、できるだけ長く稼いでいきたい。


Our Daily Life 職場の日常
職場の日常は質素ですが、日々堅実にコツコツと取り組んでいます。
----------
01 「おはようございます。」
みんなの顔を見ながら、穏やかに一週間が始まる。
月曜の朝は、9:00に役職員みんなで集まります。ラジオの音を消してから、一言ずつ挨拶を交わし、一週間が始まります。そのあと、9:15から最大2時間前後、同じメンバーで業務の進捗確認、情報交換などを目的とした会議を行います。
「〇〇さん、ちょっといいですか。」、「この案件、どうしようか。」意見や重要な情報はメールではなく直接会話で届ける、役職員の距離が近い職場です。「このタンカン、会長からです!」、「昨日のサッカー、さすがに疲れましたよ(笑)」、「今年の忘年会の場所、迷うよね~。」黙々と仕事をする中にも、ふとした会話がある雰囲気です。
----------
02 「お先に失礼します。」
静かな声掛けで1日が終わる。
仕事の大まかな予定は、全員の予定が一目で分かる電子カレンダーに前もって記入し、情報共有と分担を行っています。細かい内容については、随時進捗確認と調整をしていますので、たいてい、繁忙期以外は17:30~18:00、繁忙期でも18:00~19:00頃には、上司、部下によらず各々のペースで持ち場を離れています。
12:00~13:00の休憩時間には消灯していますので、互いに干渉することはあまりなく、食事のあとは仮眠をとる人が大半です。勤怠記録には電子システムを導入しており、PCでもスマホでも操作できます。もちろん事前申請が原則ですが、急な打合せ等のための直行や直帰、テレワークなど、直前に変更申請することもできます。なお、当社は「ユースエール企業」にも認定されています。
※ユースエール認定制度とは『若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度』です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html
----------
03 「資格試験の講習会に行ってきますね。」
業務時間内にもしっかり勉強する。
年間を通じて、毎週のように、誰かは外部研修等に参加しています。建設分野の研修、資格試験の講習会など、業務に直接役立つものはもちろんのこと、関連知識も含め、基本的には業務の一環として積極的に勉強をしています。2024年度の業務時間内における外部研修の時間は、●±●時間(N=●)です。研修、講習の参加費、交通費等は全て支給しています。
詳細については、福利厚生・その他制度のページをご覧ください→
----------
04 「ちょっと計算条件、確認しましょうか。」
OJTをベースとして、疑問点はその場で解決する。
月曜日9:15からの会議では、今週と来週の主なスケジュールの確認、業務ごとの進捗状況の確認、営業案件や外部研修、技術的トピックス等の情報共有を行っています。疑問に感じたことや重要なことは、できるだけ後回しにせず、その都度互いに納得できるまで確認し、解決に努めています。そのほか、技術的事項、安全管理、SDGs等に関する情報は、随時メール等で共有し合っています。
「先週のあの件、どうなったかな。」、「なんでこうなるんだろう」、「計算条件はどうなってますか。」会議中の些細な気づきを発端として、自然に技術講習会が始まるのが当社の日常です。ベテラン技術者からの重要な指導事項は、技術継承を意識してしっかりエクセルシートにとりまとめます。
----------
05 「ついでに寄ってから行きましょうか。」
外出時には、たいてい現場研修も行う。
当社では、測量、磁気探査、土質調査、環境調査、計画、設計、施工管理(現場技術)、機能保全計画・調査(維持管理)ほか、海辺のインフラ等整備に関わるあらゆる業務を行っています。こうした多岐にわたる業務を一貫して担うことで、分業制では得られない幅広い知識と経験が培われ、包括的な設計技術が養われます。
「計画地周辺の流況を見に行ってみよう。」、「施設の劣化状況はどうなっているかな。」、「サンゴはどのぐらい成育しているだろうか。」打合せ等の際には、当たり前のように現場にも赴き、業務へのヒントや気づきを得るための視察と研修を行います。
Data
データで見る大栄コンサルタント
□創業年数:満32年(1992年より)
-創業以来、30年間以上沖縄のインフラ整備に貢献してきています。
□職員数:●人(2025年3月現在)
-少人数ならではの柔軟な連携性や機動性を活かすことに努め、仕事をしています。
□残業時間(2024年度実績)
-一人ひとりが心身ともに健康に働けるよう意識して、互いに補助し合っています。
4月~11月(平常期):●±●時間/人/月
12月~3月(繁忙期):●±●時間/人/月
□公的業務の手持ち案件数:●±●件/人/年(2024年度実績)
-案件の特性および一人ひとりの資質や家庭の事情等を踏まえ、過不足のない成果が出せるよう手持ち案件数を調整しています。
注)計算には技術系職員●人分の値を用いています。
□業務時間内の研修時間:●±●時間/人/年(2024年度実績)
-社内外での研修を重要な業務として位置付け、職員の資質向上を応援しています。
□休日取得日数:●±●日/人/年(2024年度実績)
-完全週休2日制および祝祭日、年末年始等を休みにしています。
注)休日取得日数には、有給休暇取得日数も含みます。
□有給休暇取得日数:●±●日/人/年(2024年度実績)
-役職員全員の予定が一目で分かる電子カレンダーに、前もって各々が休暇希望日を入力し、計画的に調整しています。
□福利厚生・その他制度の種類数:●種類(2025年3月現在)
-働く基盤となる制度の整備と改善に努めています。
□賞与の回数:3回/年(2024年度実績)
-20●年以降連続して、3回/年の賞与を支給しています。
(↓↓↓全体に掛かる注意書きとして)
※平均値±標準偏差。
※手持ち業務件数を除く全ての計算には、管理職層の職員も含む●人分の値を用いています。


Feature 04
資格習得は手厚く支援
受験支援として勉強会を行ったり、社外セミナー等への参加費用は会社が負担し奨励しております。また、所定資格の受講料・受験料・交通費を全額支給し、安心して受験を受けることができます。さらに、所定資格の取得に伴い、資格手当を毎月支給しています。